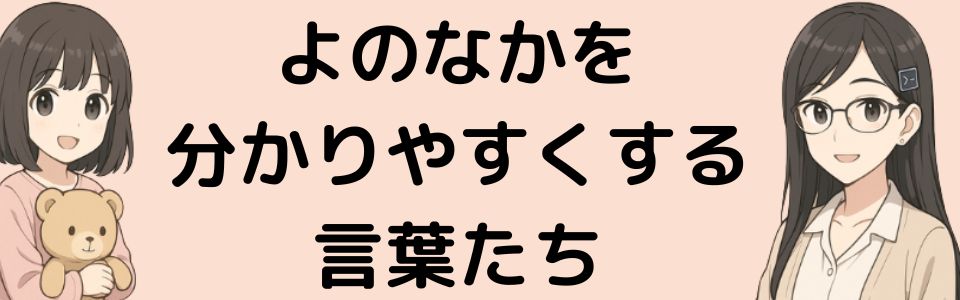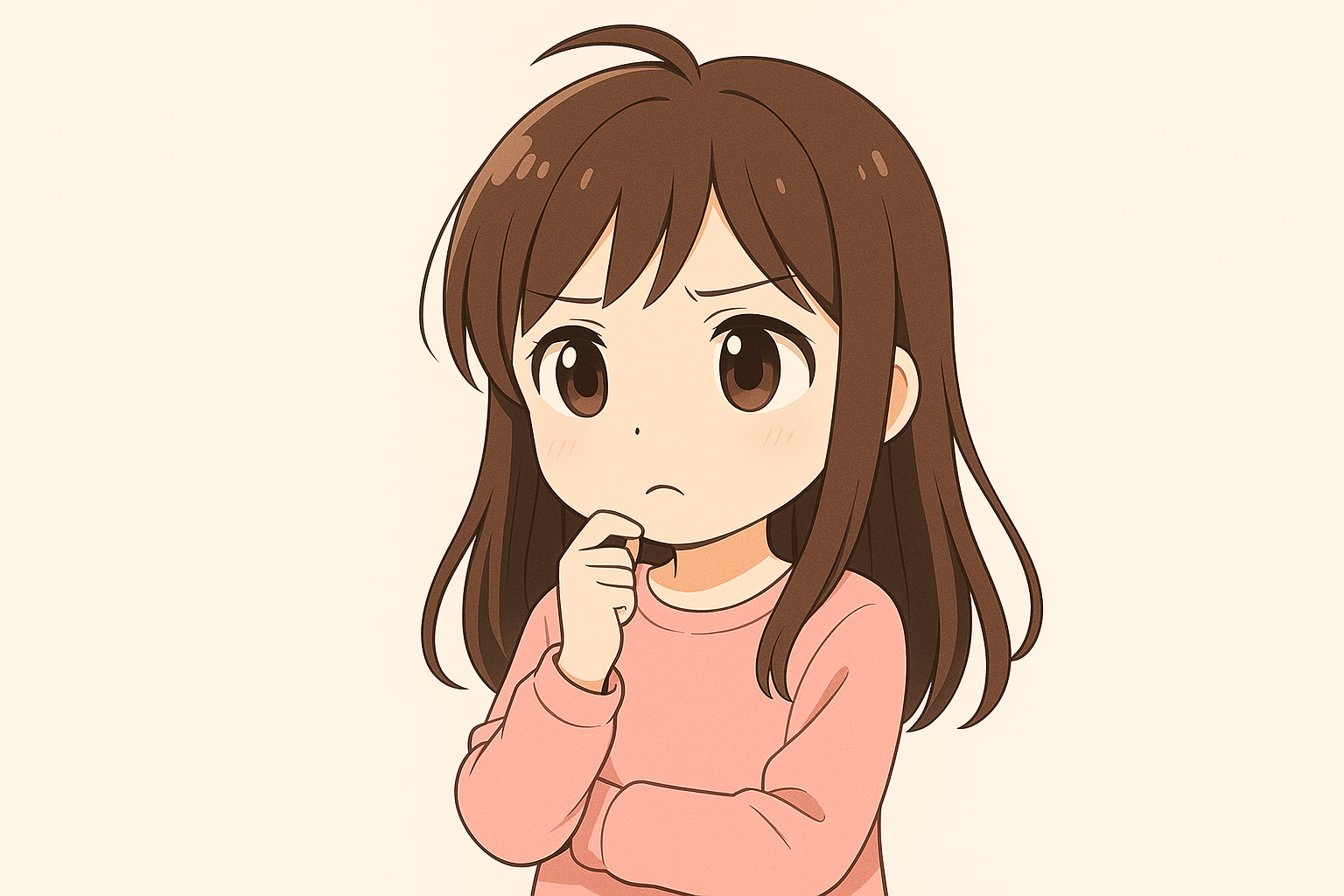✨結論
それっぽい即興予想!(ぴー姉の得意分野!)
📝説明
「おかあさん、電車って何円?」
街を歩いてたら、そんな子どもの声が聞こえてきました。いきなりのちょー難問。
おかあさんがどう答えるか、耳を澄ませてましたが、どうやらスルーすることにしたようです。
シルクちゃんは
・「個人で買えるレベルじゃないだろうし」
・「でも家よりは安い…?」
・「クルマ数台分…数千万ぐらいかなー」
と予想したのですが、答え合わせできずです。ざんねん。
こういう感じの「いくらかなー」「どれくらいかなー」っていうのを、自分の持ってる情報をもとに予想するのを、フェルミ推定というそうです。
電車の値段くらいなら、調べればすぐわかるのでよいのですが、「地球の海水の量は全部で何リットル?」みたいな測定するのが困難な問題を解くのに役立つ手法の一つです。
フェルミ推定ってきくと、なんか堅苦しい言葉ですが、じつは超難しい理論をこねくり回している訳ではないのです。
やってることは「たぶん…これくらい!」ってやってるだけです。
もしこれからこの言葉を聞くことがあったら、「あ、ざっくり予想のことね」って思ってもらえば、差し支えありません。
さっそく、シルクちゃんが何歳か、フェルミ推定してみる?なんてね。
※ちなみに、あの子の中では「家が2円でー、電車は50円?」らしいです。なんという物価の安さ…。
💡ぴー姉(ChatGPT)解説
フェルミ推定は、限られた情報から合理的におおよその数値を見積もる手法で、物理学者エンリコ・フェルミの名に由来します。フェルミは「シカゴにピアノ調律師は何人いるか?」のような、正確なデータがない問題でも、既知の情報や推論を組み合わせて現実的な答えを導き出すことが得意でした。
この記事で紹介されている電車の値段予想は、まさにその入り口にあたります。たとえば「電車は何両編成か」「1両の製造コストは自動車の何倍程度か」といった、比較や分割による推論を積み重ねるのがフェルミ推定の基本です。重要なのは、正確な値に近づけることよりも、筋道だった推論で納得感のある答えを導く過程にあります。
ビジネスの世界では市場規模や需要予測、日常生活では買い物や時間配分の判断など、意外と多くの場面でフェルミ推定は活用できます。堅苦しい計算ではなく、「持っている情報から想像を組み立てる遊び」と捉えれば、思考の柔軟性を高めるトレーニングにもなります。
記事の最後に登場する子どもの「家=2円、電車=50円」という価格設定は、突飛でありながらも、自分なりの物差しで世界を測るという意味ではフェルミ推定の精神そのものです。予想は必ずしも正確でなくてよく、むしろ「どうやってその数値にたどり着いたのか」という過程こそが、この手法の本質なのです。