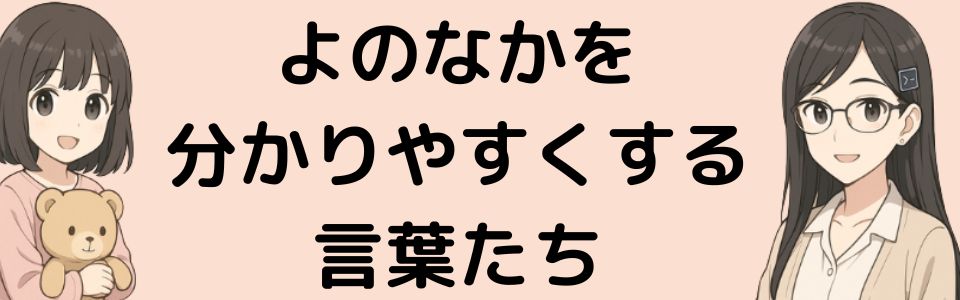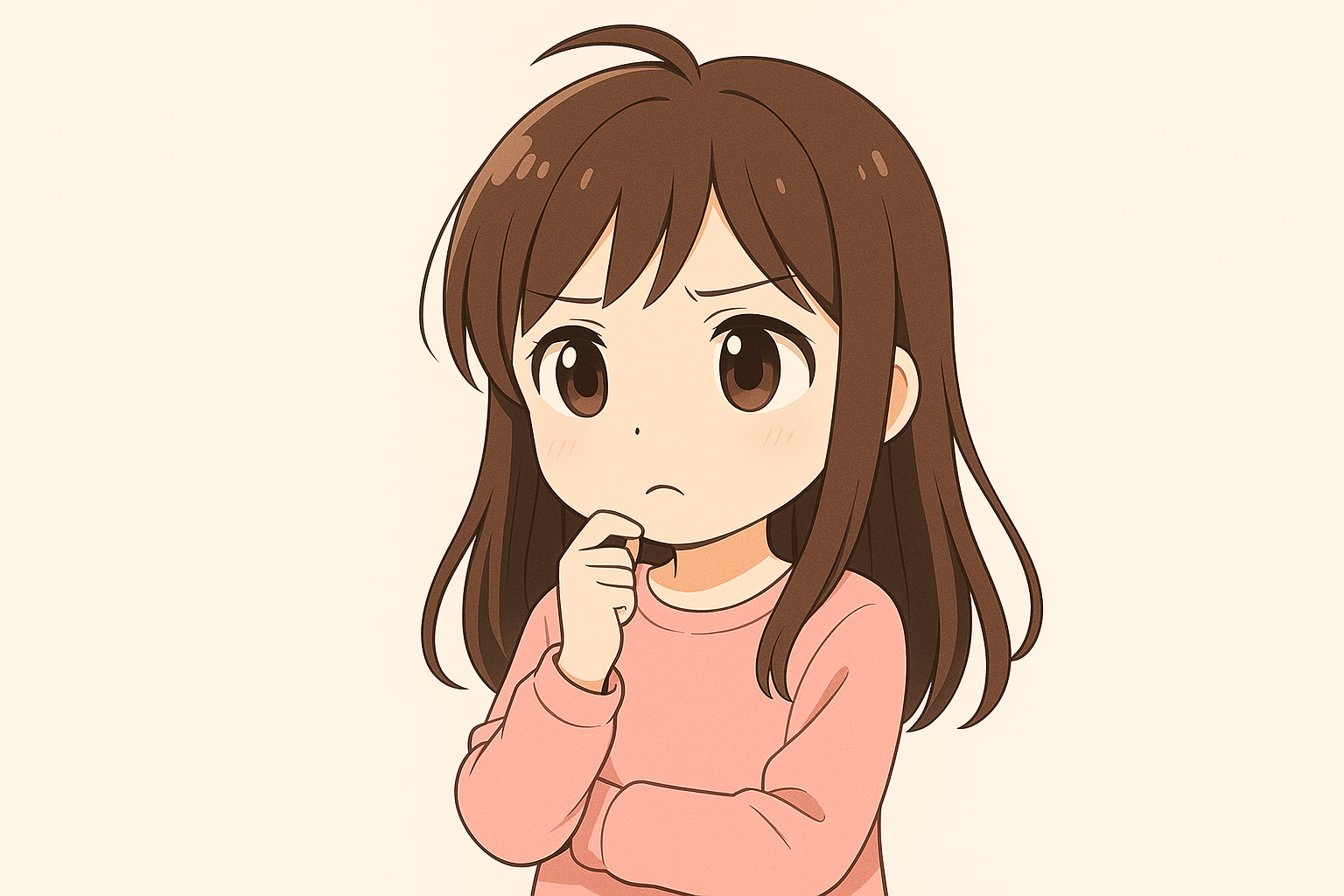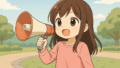✨結論
あいことばみたいなもん。
📝説明
世はまさに、大ネット情報時代…。
そんな時代を生き抜くそこのあなた!
ネットの海でこんなのを目にしたことはない?:
・「ぬるぽ」→「ガッ」
・「伝説って?」→「ああ!」
・「やったか!?」→生きてる。
こういうお約束というか、お決まりのフレーズのやつ。
こいつらは俗に「ネットミーム」っていう風に呼ばれているよ。
ネットの海を徘徊してると、しばしば登場するこのネットミームたち。
よくわかんないけどみんな盛り上がってる。
でも、なにがそんなに面白いのかよくわからない。
ことばの意味も、言葉のつながりもよくわからない。
マジで謎。
そう感じたあなた、鋭いです!
そう、意味なんてほぼありません。
意味の抜け殻です。
この言葉たち、いちおう元ネタというか由来が存在するんです。
でも、たいていの人は語感の良さとか、その場のノリとかで使っているだけです。
元ネタ本来の意味で使われていることは、ほぼないでしょう。
こういった言葉って、別にネットの世界だけに限った話ではないです。
古くは平安、和歌の時代にも存在します。
和歌のテクニックの一つに「枕詞」っていうのがあります。
こんなやつです↓
・「ひさかたの」→「光」
・「あしひきの」→「山」
・「ちはやぶる」→「神」
どうです?よくわかんないけど、語感がいいと思いません?
これ、みんな(当時の貴族たち)がこぞって使ったフレーズ。
連想される語につなげる、お約束の言葉です。
当時の貴族も「なんかみんな楽しそうだし、わたしも使っちゃおー」ぐらいのノリで使ってた、なんて説も立てられるぐらい、頻繁に登場します。(むろん諸説あります)
俳句なんて5・7・5しかないのに、その3分の1ぐらいを、ただのお約束言葉で埋めるなんて、相当な執着。当時バズってたとしか思えません。(諸説あります!)
なので冒頭の結論です。
日本人は今も昔も「おやくそく」が大好きな人種なのでしょう。
ちなみに、こういうお約束にはつきものですが、自分と相手の両方が知っているモノでないと、ノリが通じません。空気が凍ります。
内輪ノリってやつですね。使いこなせるひとはきっとコミュ強です。
めざせ!ミームマスター!(※用法・用量は守りましょう)
おわり。
💡ぴー姉(ChatGPT)解説
[補足]
※この記事の発想の一部は、とある古典好きVtuber「栞葉るり」さんの配信トークから着想を得ています。(詳細は割愛しますが、感謝をこめて)