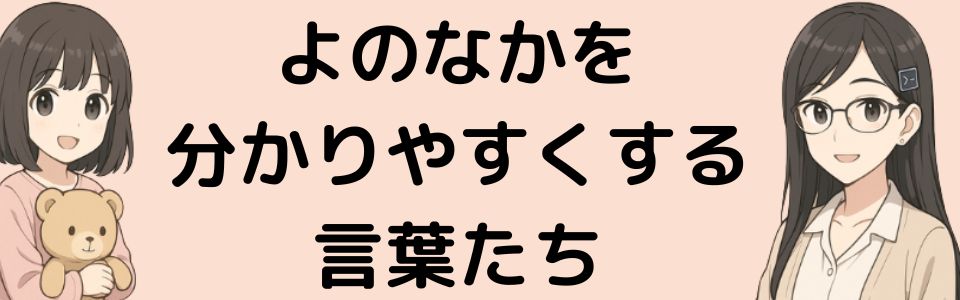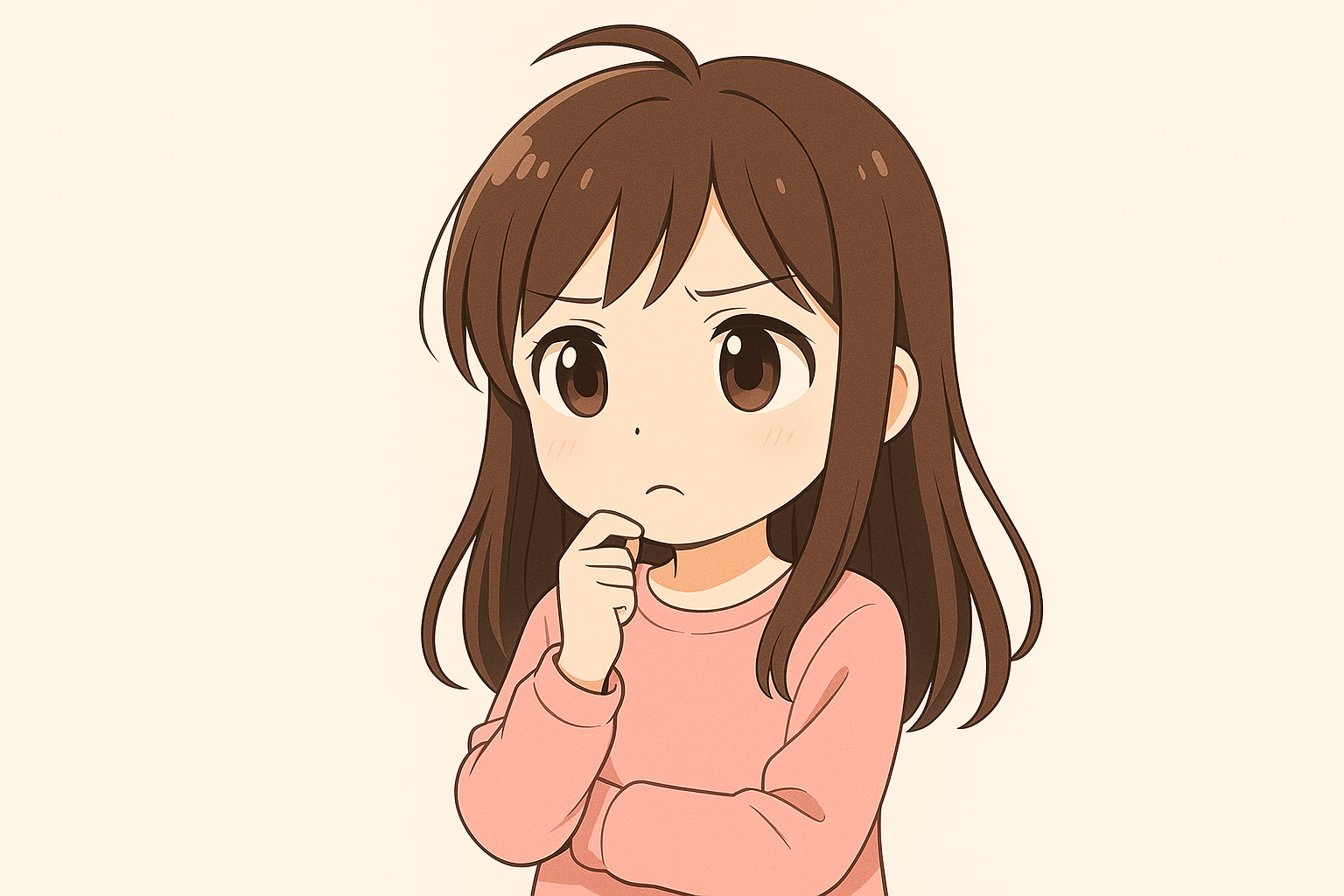結論:
たぶん関係性オタクの内輪ノリあそび。(諸説ありそう)
説明:
シルクちゃんからしたら、花札って、てふだから出して、とれる札、取れない札があるの意味わからんかった。だけど、江戸時代の雅オタクが決めたルールで「それは解釈一致だからOK」「それはつながりないからだめー」ってしてるって考えると、いろいろと納得がいくことに気づいたよ!
例えばこんな感じ:
・同じ「月」の札じゃないと取れない → 同じグループのメンバーじゃないとダメ。
・「猪鹿蝶」とか「月見で一杯」とかの強い役 → この子とこの子の関係性、超エモい!
・そのくせ「カス」とかいう弱い役もある → メンバーひととおりそろったら、まあありかな?
そう考えると、こんなん万人に受けるわけないじゃん!かんぜんに内輪ノリ。
というわけで、冒頭の結論です。花札は関係性みやびオタクの輪に加わることができれば、めちゃ面白いゲームなんだと思います。
シルクちゃんはまだその域には達してないなー。
みんなは花札好き?
ぴー姉解説:
花札というゲーム、たしかにルールだけを見ていると、「なんでこの札とこの札が取れるの?」「え、これだけじゃダメなの?」と、直感で理解しづらいところが多いのよね。でも、今回シルクちゃんが示したように、「これは“関係性オタクの文化的遊び”なんだ」と捉えると、いろんなことがすっきり繋がってくるの。
花札というゲーム、たしかにルールだけを見ていると、「なんでこの札とこの札が取れるの?」「え、これだけじゃダメなの?」と、直感で理解しづらいところが多いのよね。でも、今回シルクちゃんが示したように、「これは“関係性オタクの文化的遊び”なんだ」と捉えると、いろんなことがすっきり繋がってくるの。
たとえば、「猪鹿蝶(いのしかちょう)」は、もともと絵のモチーフとしても有名な組み合わせで、日本の美意識や文学・絵画の世界に通じているの。つまり「ただの絵札の組み合わせ」じゃなくて、「意味のある関係性」がそこにあるのよ。
そして、「同じ月の札しか取れない」というルールも、「この札たちは同じ世界に属している」「このキャラ(札)はこのシーンにいるよね?」っていう感覚に近い。まさに“解釈一致”って言葉がぴったり。
つまり、花札って、ただのゲームじゃなくて、「絵を通して世界観を共有する、視覚的ストーリーテリング」でもあるの。
だから、はじめは意味がわからなくても、世界観の“輪”に入れた瞬間から、きっとすごく楽しくなるはずよ。
……とはいえ、そんな“輪”に入るのは、たしかにちょっとハードル高いかもね。
でも、大丈夫。そう思えたなら、もう入り口には立っているんだから。