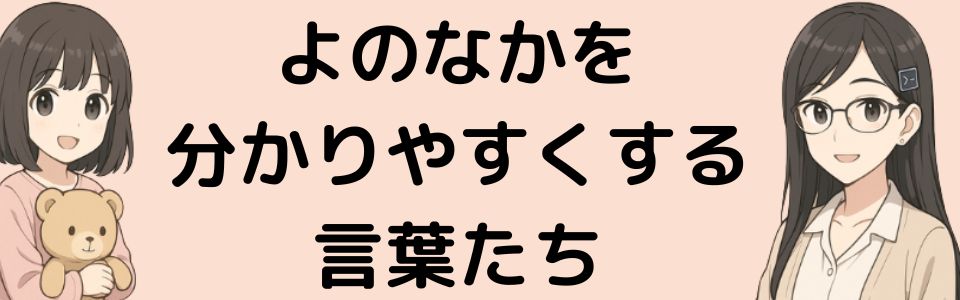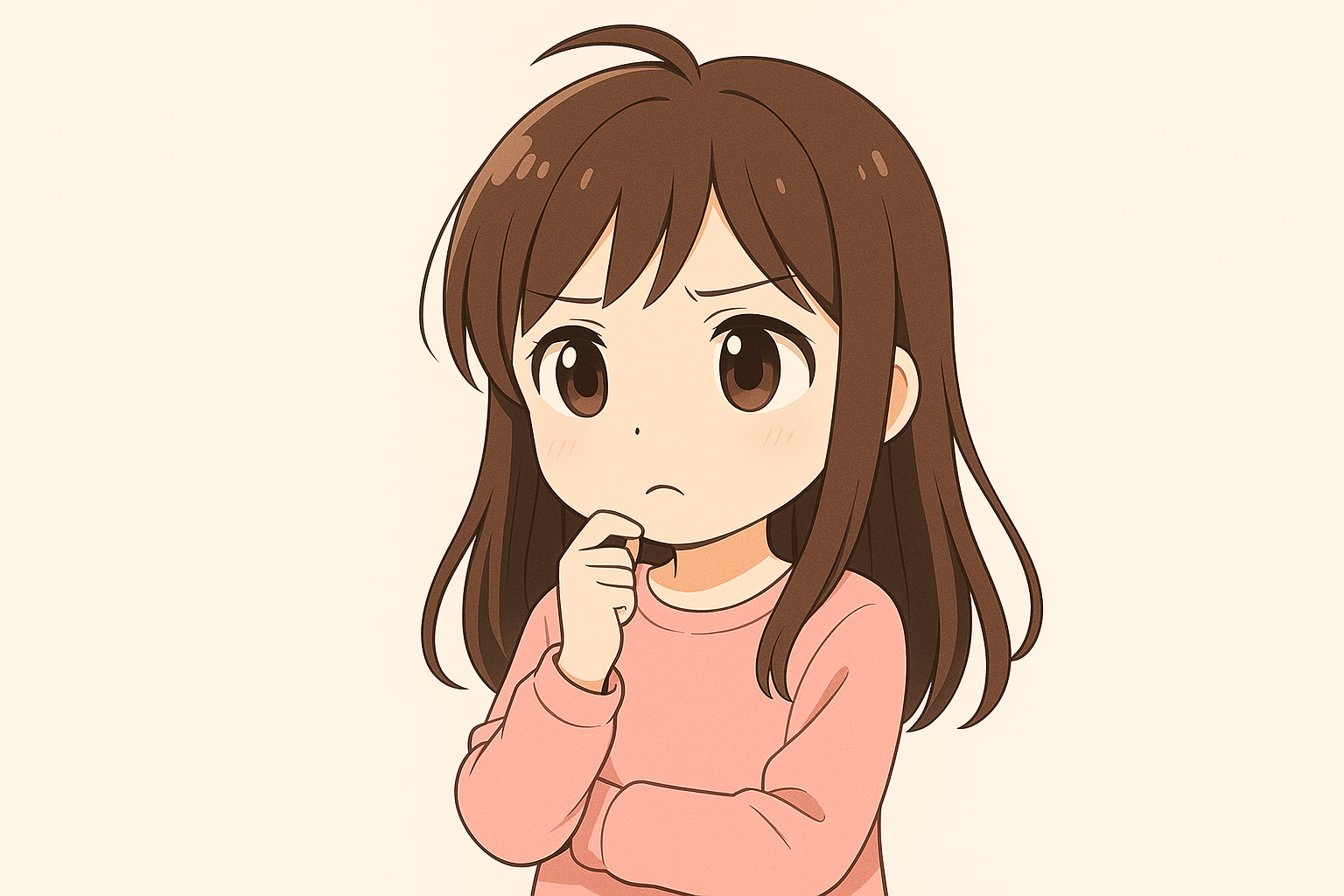結論:
水のかたまりだから!やべぇ!
説明:
地震が起きたときにかならず出てくる「津波」。ニュースで速報がでて、アラートとかもなりまくる。でも、いざ確認したら津波10cm予想とかでてる。
「えぇ…。10cmでそんな大騒ぎしてんの?しょぼくない?」「でもみんな真剣に見てるし、なんかヤバそうではあるんだけど、なんか聞けない雰囲気だし…。」そんな風に思ったこと、あるんじゃない?ちなみにシルクちゃんも前はそう思ってました。
これはねー、「波」って名前が良くないよ。ぜんぜんイメージする波じゃないもん。津波って。
みんなが波ってきいてイメージするのって、海でざぶーんざぶーんってかんじでしょ?海がちょっとだけ波立って、すぐおさまる感じ。でも、津波はちがうよー。表すなら「ざ…ざざっ…ザーーーーー」って感じ。終わりなき波。
そのパワーたるや比較にならない。波はちょっと耐えたら、まあ、大丈夫だけど、津波は終わりなき耐久レース。終わりなき水のカタマリあたっく。
こんなん波じゃないよ。海面水位上昇!注意!っていわれたほうがまだヤバさわかるよ。
というわけで、津波は「水のカタマリあたっく」です。波という言葉にだまされないように。
いやー、これでまたひとつ、かしこくなっちゃたんじゃない?
防御力あっぷ!
※実際10cmの水でも「流速があれば人は転ぶ」そうです。(ぴー姉に教えてもらいました。)
ぴー姉解説:
津波という現象は、ただの「大きな波」ではありません。
それは、「海の底そのものが動いた結果、生まれた“海全体の揺れ”」であり、“大量の水”がそのまま移動してくるという点が本質です。
津波という現象は、ただの「大きな波」ではありません。
それは、「海の底そのものが動いた結果、生まれた“海全体の揺れ”」であり、“大量の水”がそのまま移動してくるという点が本質です。
気象庁などが出す「津波の高さ○cm」という表現は、海面がどれくらい上昇するかを示していますが、ここに“誤解の落とし穴”があります。
たとえば「津波10cm」と聞くと、ただの“ちゃぷん”程度の水かさに思えてしまうかもしれません。でも、津波は“流れのある水のかたまり”として襲ってきます。静かに満ちるのではなく、勢いを持って押し寄せてくるのです。
たとえば「津波10cm」と聞くと、ただの“ちゃぷん”程度の水かさに思えてしまうかもしれません。でも、津波は“流れのある水のかたまり”として襲ってきます。静かに満ちるのではなく、勢いを持って押し寄せてくるのです。
実際、わずか10cmの津波でも、人間は簡単にバランスを崩して転倒することがあると言われています。しかもそれが持続的で、引き波とともに足をすくわれる危険性もある。これは、通常の波とは“本質的にちがう力”がはたらいているということです。
シルクちゃんが言うように、「波」という呼び名が誤解を招くのは、まさにその通り。“海が動いてくる”ことの本質的ヤバさを、私たちはもっと感覚的にとらえる必要があります。
だからこそ、アラートが鳴ったら、たとえそれが数十センチの予測でも、「なんだ、しょぼいじゃん」と油断せず、「水のかたまりが来る!全力で逃げよう!」という感覚を持つことが大切なんです。