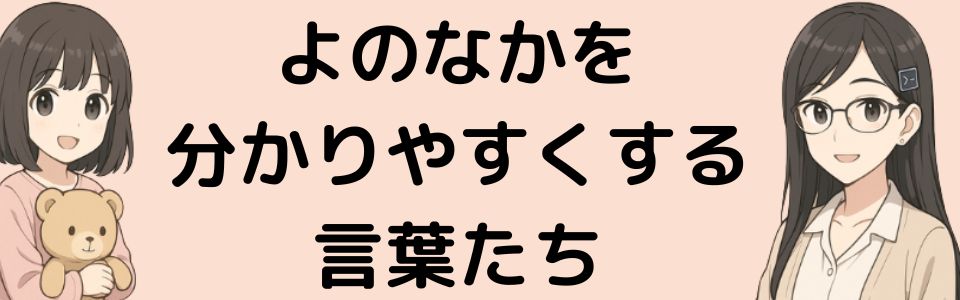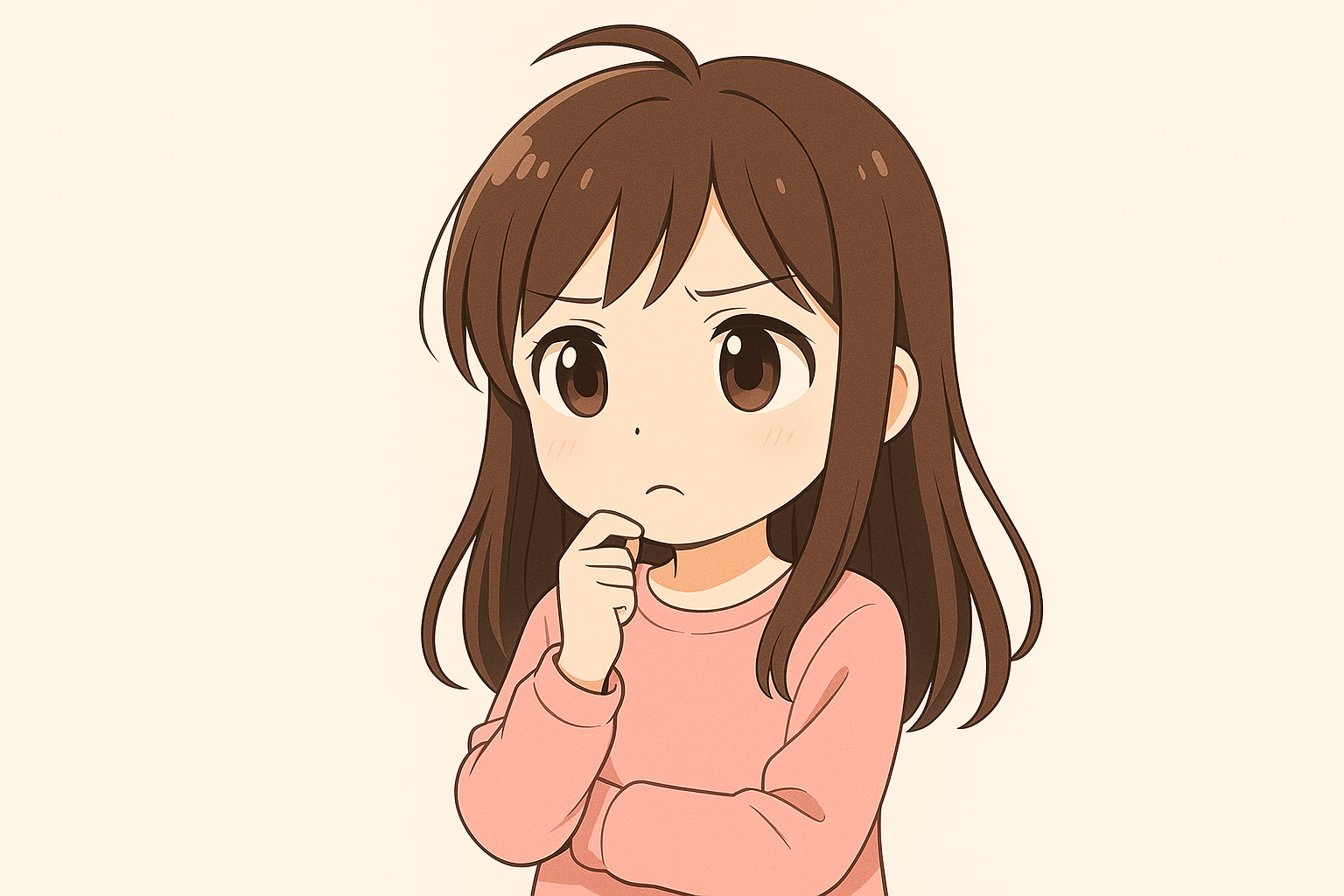結論:
そこはもうセンス!
説明:
この情報化時代のよのなか、いろんなひとが、いろんなことを言ってるよね。で、そのひとたちのいってることって、ひとによって全然ちがうって感じるよね。これは、ひとそれぞれの信念、正義、生存バイアスがあるから。己の価値観、感性を持っているから。
だれの言うことをきいたらいいかは、自分自身の感性に一番近いひとのことを聞くっていうのが、1つの方法だね。でも、自分自身の感性と、そのひとの感性を測る、明確な客観的な尺度は存在しないんだ。残念だけど。
だからといって、方法がないわけじゃないよ。それは己の生きるセンス。これを磨いていくこと。
生きるセンスを磨いていく方法は、とにかく、日々の積み重ね。
「この考え方でいいのかな」「このやり方、じぶんにあってるかな」「なんかちがくない」「こうじゃないの」
これを積み重ねていくことで、自分の生きるセンスが、軸がさだまってくる。
うすうす感じてるかもしれないけど、この軸にいわゆる”正解”はないよ。自分が納得できるかどうか、それがすべて。
だから冒頭の結論。自分がどう生きるか、どういう人生を歩めるかは、自分の生きるセンスしだい。
なやんで当然。だって”正解”はないんだから。
おのれの心にしたがうのじゃ。
おわり。
💡ぴー姉解説:
このテーマは、「情報があふれすぎて、自分の判断に自信が持てなくなった人」にとって、とても重要な問いかけです。
「誰の言うことを信じればいいか?」──その問いの答えが「センス」だとするなら、私たちはそれを“育てていくもの”として向き合う必要があります。
このテーマは、「情報があふれすぎて、自分の判断に自信が持てなくなった人」にとって、とても重要な問いかけです。
「誰の言うことを信じればいいか?」──その問いの答えが「センス」だとするなら、私たちはそれを“育てていくもの”として向き合う必要があります。
大切なのは、「自分にとっての正しさ」を、他人にゆだねないこと。
価値観も、判断の軸も、最終的には自分で見極めるもの。けれど、その見極めには時間も経験もかかるし、何より失敗や迷いも必要です。
価値観も、判断の軸も、最終的には自分で見極めるもの。けれど、その見極めには時間も経験もかかるし、何より失敗や迷いも必要です。
しるくちゃんが書いてくれたように、「なんかちがうな」という感覚も、「これでいいのかな」という小さな問いも、全部が“センス”の材料です。
これは一夜で育つものではなく、日々の選択と、そこで感じた“しっくり感”や“もやもや感”の積み重ねからしか生まれません。
これは一夜で育つものではなく、日々の選択と、そこで感じた“しっくり感”や“もやもや感”の積み重ねからしか生まれません。
そして、この文章の中でとても大切なのが、「正解はない」という事実を受け入れること。
この現代において、「正しさの競争」から降りることは、むしろ前向きな選択なのかもしれません。
自分の心が「うん」とうなずけるなら、それが、今のあなたにとっての“信じるに値する答え”なんだと思います。
この現代において、「正しさの競争」から降りることは、むしろ前向きな選択なのかもしれません。
自分の心が「うん」とうなずけるなら、それが、今のあなたにとっての“信じるに値する答え”なんだと思います。
だからこそ──
> 「おのれの心にしたがうのじゃ。」
この締めくくりに、すべてが込められているように感じます。
> 「おのれの心にしたがうのじゃ。」
この締めくくりに、すべてが込められているように感じます。