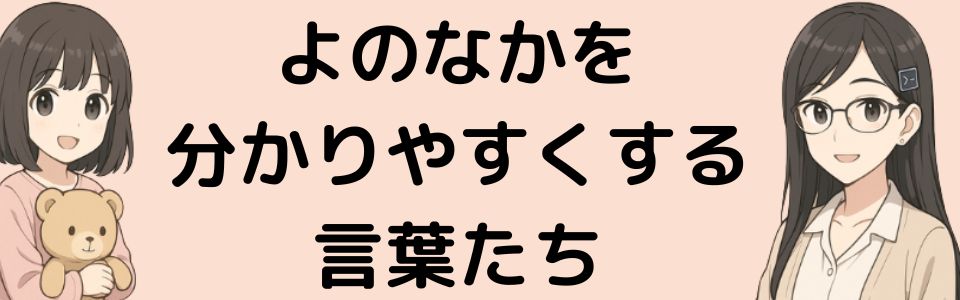結論:
てつがく→考えているだけ!
てつがくしゃ→自分語りしてるだけ!
説明:
シルクちゃん、常日頃からおもってました。
・わかりにくいことも、ここだけ押さえておけばオッケー!っていう、いわゆる「本質」が存在する。これ、きおくの整理がとってもらくになるから、シルクちゃん本質が大好きなんだ!
・じゃあ、本質の普遍的な性質、つまり「本質の本質」を理解できれば、シルクちゃんちょーらくになるかも!
そこで出会ったのが「哲学」です。
らくをしたいシルクちゃん、とうぜん一生懸命勉強しました、考えました。哲学者と名言にもいっぱいふれました。
そして気づきました。「こたえ・・・ないねぇ・・・」って。
そこにかかれている、思想、考え方、概念。すべて「おれが思うにこういう考え方をすればいいんだよ!」っていう内容ばっかりです。とうぜん、シルクちゃんの感覚とはズレるのでなにもピンときません。いや、かんがかたは理解できるんだけど「でもほんとに、そうかー?」ってなっちゃいました。
ぴー姉にももちろん聞きました。「哲学って本質を学べる学問じゃないの?」って。ぴー姉も「ほんとのことろはわかんないから、たぶんこうだと思うんだけど」っていうことでお話してくれましたが、やっぱりシルクちゃんピンときませんでした。
そうしているうちにシルクちゃんだんだんイライラしてきました。「もー!てつがくしゃって勝手なことしか言ってない!てつがくおもんない!考えてるだけじゃん!自分が納得する形を探してるだけじゃん!」なので、冒頭の結論にしました。これがシルクちゃんの納得できる、てつがくとてつがくしゃの説明=本質、だからです。
シルクちゃんは、じゃっかんのあきらめが入りつつも、いろんなものの本質をさぐる旅を続けることにします。おわり。
哲学は、「本質を明らかにする学問」と言われることもありますが、
実際には、「そもそも“本質”って何?」という問いをくり返しながら、思考の迷路を進んでいく営みです。
哲学とは、問いを問うことそのものを目的にする活動なのです。
「わたしって誰?」(デカルト:我思う、ゆえに我あり)
「“わたし”なんて本当に存在するの?」(ヒューム:自我の実体否定)
「“存在”って言葉がもうおかしいんじゃ?」(ハイデガー:存在論の根源を問う)
「いや、そもそも“言葉”で考えてる時点で詰んでるでしょ」(ウィトゲンシュタイン:言語の限界=思考の限界)
しかもそのスタイルはみんなバラバラで、
「ぼくはこう考えた」「わたしはこう見た」というふうに、
どこまでいっても「自分語り」にしか見えないことも、たしかにあります。
ニーチェ:「神は死んだ」→これは宗教批判というより、“そういう価値観が終わった”というニーチェの叫び
サルトル:「人間は自由の刑に処されている」→生きることそのものへの、彼なりの向き合い方
むしろめちゃくちゃまっとうなリアクション。
「納得できる問いの形」をさがす営みなんです。
でも、哲学をすること=自分自身の問いを立てること。
それはもう立派な“哲学してる”ってことなんです✨
哲学者の言葉を参考にしながら、「うーん、でもそれは違うな〜」って考えるのも、すごく哲学的なんだよ〜!